中国木刻論
石飛仁が劇団エリトゲをはじめたのは、強制連行事件総体を明らかにするためである。花岡反乱にしぼったのは一点突破するためである。一点突破するためのドリルに硬質のヤキをいれるために、エリトゲは日本最小のアジプロ劇団の方法を選んだ。
民衆的アジプロの方法として、エリトゲの活動は、中国紅軍が延安や新四軍根拠地から中国本土に発したパンフレット、新聞、各種ビラに刷り込まれた木版画に比肩するものに成長するだろう。
この二つの目に見えぬ糸があるように感じる。劇団エリトゲが背景に映写するスライドに、花岡事件の様子を刻んだ木版画がある。これは洛澤『花岡川の嵐』邦訳版に収録された十葉の木版画からとられたものである。この木版画に関して訳者立花祥介の解説にいわく。
「また挿画に使用した中国語版『花岡惨案』(中国・人民美術出版社・一九五六年刊)は、井口晃氏のご蔵書を利用させていただいたものである」その版画作者はわからなかった。たぶん中国人だろうと思っていた。版画に題名はないが、キャプションがあって、そのいくつかを紹介すると、
川の水を飲む中国人捕虜に後ろから日本人棒頭が棍棒をふるう図に「水路改修の激しい過重労働の上に、日本人補導員たちは過酷な虐待を中国人に加えた」。
山東省における労工狩りの図に、「日本国は国内の労働力不足を補うため、中国大陸で労働者、農民を狩り出し、俘虜とともに日本へ強制連行した」。
通訳任鳳岐殺害の図、「六月三十日の深夜、中山寮の中国人たちは、”抗日別働隊”を組織して蜂起、まず売国奴の” 漢奸”らを打倒した」。
獅子ヶ森の抵抗戦の図。「秋葉山に立てこもった蜂起軍は厳重な包囲網のなかで二日間、激烈に戦った。主な武器は大小の石ころであった」。
日本刀の鎮圧側に対し銃の台尻をふりあげて抵抗するは白兵戦の図。「衆寡黙せず、武器、食料も尽きて山頂でついに肉弾戦。英雄的な戦士は敵側の武器を奪って最後まで奮闘した」。
版画はすばらしくよい。学生時代、さねとう・けいじゅうの本で、抗日戦下の中国版画について読んだ記憶もあって(本の名を失念)、素朴だが、光と闇とによって主題をくっきりとらえる作風はあきらかに中国産とおもわれた。
そしてこの版画には多少の事実誤認があって、たとえば中国人蜂起者が立てこもったのが「秋葉山」となっているが、反乱者たちは「獅子ヶ森」を秋葉山とかんちがいしていたのである。そのことは訳者も指摘している。より詳しく言うと、かれらは脊梁山脈の一角たる秋葉山に逃げ込んで山岳ゲリラ戦を行う計画だったが、二百メートルほどの孤立した小高い獅子ヶ森を秋葉山とまちがえて立てこもったために、日本側に包囲されたのである。また、銃を奪取する計画はあったが、米軍捕虜収容所の開放に失敗し、そこにあった銃器を手に入れることはできなかった。それらのことは劇中で石飛仁は補足説明して芝居を続けている。
近年、中国人が刻んだものと思っていた木版が、日本人画家、新居公治、詩人牧大介、切り絵画家滝平二郎の手になるものであり、版木も日本に現存することが明らかにされた。
中国版『花岡惨案』は、昭和二十六年に三氏が出した版画詩集『花岡ものがたり』の翻訳だったのである。このことを報じた『大館新報』(昭和五十六年五月十二日号)を引用する。
“幻の版木”三十年目の問い
『花岡ものがたり』の取材は二十五年秋に始まった。敗戦の傷跡がまだ生々しい中、花岡事件が一行も報道されず、いまわしい事件とされて地元の人たちは口にもしなかったが、重い口から多くの証言を得た。
取材したのは、水戸市の画家で、鹿角市毛馬内出身の牧大介氏、七年前ガンで亡くなった水戸市の版画家・新居広治氏の二人、二ヶ月後、きり絵で知られる滝平二郎氏も参加している。”弾圧”も厳しかったらしく取材の方法は隠密だったようだ。が、牧氏らは旧制大館中学校に通うため共楽館と関係があり、この経験を生かして同級生たちにアタック、タブーに挑んだという。
三人はその後、横手市内の支持者宅にこもった。下絵は新居氏が描き、滝平氏が彫る。牧氏は文中の秋田弁をなおしたり、版木を東京で調達したり資金を集めた。約半年というもの、コッペパンとどぶろくの毎日だった。
版木はすぐに印刷できるように、サクラの板を二枚張り合わせ、活字の高さにしてある。版木の入手には、中国版画運動の父・魯迅と親交のあった内山完造氏の弟、内山嘉吉氏の力が大きかった。
詩集ができたのは二十六年五月。五十七枚の版画と詩を組み合わせ、横見開の体裁で一一〇ページ。中日友好協会編とあるだけで作者名は入っていない。表紙うらの歌も作者不詳だ。そのまま絶版となったが、五年後、中国で版画をそのまま入れて翻訳した「花岡惨案」が出版された。また四十一年、花岡・十瀬野公園に「日中不再戦友好碑」が建てられたのを機会に、四十六年、同碑を「護る会」によって完全復刻版が発行されている。(傍線・引用者)
この報道につづき、野添憲治らによる”幻の版木”発見のいきさつが報じられている。版木を持っていた新居広治氏が昭和四十九年、ガンで亡くなる前、宇都宮の画家、鈴木憲二氏にミカン箱に入れて預けたこと。新居氏死後、鈴木氏の手から水戸市の日本美術会会員岡野良平氏に托されていたもので、野添氏の問い合わせによって岡野宅で発見された。そして新復刻版と展示会が企画されていること。作者不詳の歌、”花岡節”は劇団わらび座主宰者原太郎氏の作曲したものであること。
俺が運命的な糸を感じたのは、『大館新聞』引用文中、傍線を附した内山嘉吉の箇所だ。魯迅の文芸活動のうち、映画、漫画、版画のしめる位置を見落としてはならない。これらはいずれも中国革命、抗日戦過程で大きな威力を発揮するのである。
現代中国版画の起点は、魯迅と内山完造の友情のうちに、完造の弟、嘉吉が魯迅主宰の一八芸社の若い美術家たちに木版画の実習講座をひらいたときにはじまっている。他の文献から引くと、「その頃、魯迅は内外の版画を苦労して集めていたので、彼のところには外国を含めて各地から貴重な版画がおくられてきた。荷物がつくたびに完造は珍しい版画を見せてもらった。」(小泉譲『魯迅と内山完造』、講談社一九七九年)。
一九三〇年十月四日と五日、上海北四川路の購買組合楼上、日語学校を展覧会場に、魯迅は内山完造の協力を得て、魯迅所蔵の約七十点の版画に、魯迅が日英中国語で注を書いて版画展覧会をひらいた。客は約四百人、ほとんどが日本人だったという。これが中国最初の版画展のようである。ただ、内山完造・奈良和夫『魯迅と木刻』(碑文出版、一九八一年)によるとその三月前の一九三〇年七月六日、「現代美術社展覧会」を魯迅は見にゆき、自分の所蔵していないソ連革命美術作品を閲覧し、一元寄付しているから、これを中国最初の版画展といっていいかもしれない。ただしそのソ連革命美術作品が、ビラ、宣伝文、版画等であることはわかっているが、どんなものが展示されたのかはわからない。
どちらを先に最初の版画展とするかということは大した問題ではないだろう。大事なのは、版画展の一年後に版画作りが始まったということであり、内山完造の弟、嘉吉の一九三一年頃の上海行きと、彼が一八芸社の美術家たちに教えたことである。嘉吉は、二科会系の彫刻家で、当時、成城学園小学校の美術教師だった。嘉吉が兄の完造夫妻と北部小学校教師に版画の手ほどきをしているのを見て、魯迅が「上海の美術学生に版画の作り方を教えてやってほしい」と言い、一九三一年八月一七日から一週間、魯迅主宰の一八芸社を中心に、講師が嘉吉、通訳は魯迅自身が担当して、一八芸社同人の野天夫、陳鉄耕、陳煙橋などをはじめとする十三人の画学生に教えたのがはじまりである。
「果たせるかな、この日こそ中国木刻運動の第一頁を飾る歴史的出発の日だったのである。そしてこの講習会の一ヶ月後に起こった九・一八事件(満州事変)、日中全面戦争そしてそれに続く中国解放戦争の中で果たした現代版画の大いなる役割とその発展は凄まじいものがあった。その最初の火つけ役をやったのが、当時全く無名の若き美術家内山嘉吉であり、魯迅の陰にあって絶えず協力をおしまなかった裏方役の内山完造という日本人であったことを重要に考えなかればならないのではないだろうか」(小泉・前掲書)
魯迅が日本の版画に注目していたことは、彼の浮世絵愛好ぶりからも推察できる。いわく。「日本の浮世絵には、これといった大きな題目などあったでしょうか。だがその芸術的価値は存在しているのです」(一九三五年二月四日付、李樺宛書簡、内山嘉吉『魯迅と木刻』より孫引き)さすが魯迅だ。浮世絵にないものは大きな主題だ。大きな主題とは階級闘争である。
魯迅、内山兄弟、一八芸社の若い美術家たちによってはじめられた木刻は、ドイツ版画、ソヴィエト版画の影響を受けて(吸収して)、急速に発展してゆく、その後の中国木版発展史は別テーマになるので省略しよう。なぜ魯迅は版画に注目したのか。
第一に彼は、中国が版画の発祥の地であり、版画は中国に帰ってくるという民族芸術の復活を信じていた。
第二に、楽しい。版画は彫ることも、刷ることも、見ることも、楽しい。
第三に、平明であり、簡便であり、文盲の多い中国民衆にアピールするためによい。
国共内戦、抗日戦の時代、革命のジャーナリズムは写真製版の機械など持っていなかった。挿絵、スローガンの視覚化はもっぱら版画で行われた。この性格が中国現代版画の画風を決定したのである。
革命のジャーナリズムの創出――この性格は魯迅にあって、漫画、映画、版画の有効性の評価と、とりくみを決定している。漫画と版画は一体のものでもあり、四人組追放後の現代中国漫画、復活した『風刺と幽黙』誌などにも依然として一コマ絵が多いのも、版画的発想だと思われる。また魯迅は「連環図画」つまり木版による物語も擁護しており、これは劇画の価値を認めるの論の魁とも読めるものである。
それはそれとして、魯迅のその作風が内山嘉吉を介して、花岡にもあらわれたのである。『大館新報』記事のつたえるように、「版木の入手には――嘉吉氏の力が大きかった」だけではあるまい。嘉吉『魯迅と木刻』には直接『花岡ものがたり』のことは出てこないが、関連する記載がある。
「いま健在な人では滝平二郎氏がある。最近『切り絵』という新しい世界を拓き、子どもの絵本、新聞の家庭向けページやTVのタイトルバックなどに美しい画面を見せて、日本の大衆に親しまれているが、この人も農民版画家である。あまり話したことはないが、この人の版画も戦後ずっと農民を描きつづけて来られたようである。最近のこの人の『切り絵』は、中国の民間伝承芸術の一つ『剪紙』(きりがみ)を版画と統合させたようなもののようである。その切り絵が日本の大衆に親しまれている現在を基盤に、きっと大衆を立ち上がらせる作品に発展されるだろうと期待を持っている」(第一章三節「中国木刻画と日本の版画家たち」)
戦後、内山嘉吉は、無着成恭のやまびこ学校の版画を指導し、農民版画、民衆版画運動に積極的に投じているから、花岡事件の記録もよく知っていたにちがいない。
嘉吉―魯迅―八芸社―中国木刻運動―抗日戦下の版画―花岡事件―花岡事件の版画詩集の出版と嘉吉の尽力、と大きく回ってきた流れはこれでつかめたと思うが、さらに細部の事実が、『日中友好新聞』一九八一年八月二日号で明らかにされているので、ふれておこう。
これはもの言いからはじまっている。野添憲治が『花岡ものがたり』の版木を発見したことが報じられたのが五月十二日の『大館新聞』、その後、彼は秋田市の出版社無明舎と組んで、近々その復刻版と、東京での版画展をひらくことと、中国でも再出版の計画があることを七月七日の朝日、読売、毎日の各秋田県版に発表した。このことに日中友好協会の大田宣也事務局長が抗議した次第が『日中友好新聞』八月二日号に載っている。
「……『花岡ものがたり』の編集と版権は日中友好協会にあるにもかかわらず、野添、安倍両氏からは協会に事前に何の話もなく、新聞報道で初めて知り驚いています。
鈴木氏の話のように『花岡ものがたり』は、故新居広治氏はじめ製作者が、侵略戦争の深い反省に立って、真の日中友好に役立つよう願って作られたものであり、協会は使用目的がこの立場に立ったものでなければならないと考えています。
日中友好協会は七月二十三日、野添、安倍両氏に対し、無断使用に対する抗議を表明、使用目的などを明らかにすることを求めた質問状を送りました。野添、安倍両氏が良識ある態度をとられることを希望します」
あまり気持ちのいい談話じゃないな。三十年も行方不明になっていた版木が出て来たところに、その発見者に向かって、おれんとこのものだから勝手に使うな、と言われてもこまるだろう。それはそれとして、版画家たちに仕事場を提供した鈴木義雄氏(花岡の地・日中不再戦友好碑をまもる会顧問)の話が、『花岡ものがたり』の成立事情をより詳しく伝えてくれる。
――一般に『花岡事件』といっていますが、なぜ「花岡ものがたり」としたのですか。
鈴木 それは、この惨事を目撃した多くの人々に、勇気をもってもらいたかったからです。一九五〇年から遺骨の収集が始まり、収集作業に参加する人が広がっていきました。遺骨をいとおしんで、故国に送り届けてくれた善意の人々に、人間への信頼をもっていただくために、ルポルタージュと創作との中間をとることが適切と考えたのです。
(中略)
私たちが出版をいそいだのは、軍部や鹿島組が、証拠いん滅に慌てて動きはじめたからです。ですから出版は時間とのせり合いでした。戦時中この虐殺を防げなかった日本人としての良心と悔いをこめて、遺骨収集とその中国への送還の大事業にとりかかりました。戦争の風化を企てる支配層への怒りが多くの人びとをとらえました。
朝鮮人労働者をはじめ失対労働者――みんな戦争犠牲者でした――が、遺骨の完全返還を求めて立ちあがりました。会社はダムをつくり、証拠をいん滅しようとする、私たちは遺骨を収集する、会社は形ばかりの慰霊碑を建てる、私たちは日中不再戦友好碑を建てる、会社は共楽館をこわして体育館を、私たちは共楽館跡地に後世に残す碑文をそえた記念碑を建てる、激しい、戦争か平和かのつばぜり合いが演じられたのです。
これはそうなのである。戦後、『軍部』とあるのは、旧軍人たちのことだが、中山寮はダムに没し、「形ばかりの慰霊塔」はコンクリート製のもので、鹿島建設はいちばん安い材料を使ったということがありありとしており、拷問のあった共楽館(映画、演劇の施設だった)は体育館になっている。企業、役人たちの証拠いん滅作業に対して民衆の側は立ちおくれている。この問題は石飛仁の展開に待つが、何点かを走り書いて問題提起する。
①強制連行されて日本国内で働かされた中国人俘虜のうち、生存者は日本敗戦後の一年以内に祖国に帰り、遺骨は一九五〇年からはじまった収集作業によって還った。それでおわりだ。
②賠償がない。労賃さえ払われていない。
③企業、国家検閲による証拠いん滅作業の実態もあきらかにされていない。『同時代批評』十三号論文で石飛仁が指摘したように、敗戦翌年一九四六年度の予算編成が鍵なのだ。
④予算編成にあたって、各企業が提出した強制連行とその労働状態をまとめた文書、いわゆる「外務省報告書」は、現存するのに、その公開を迫った野党がない。
⑤帰国した中国人たちのその後がまるで知られていない。劉連仁が山東省の人民公社に元気で働いていること、『花岡川の嵐』の作者洛澤が現存すること等を例外にして、他はわからない。帰国後、国共内戦にぶつかり、海南島で戦死した人々がいるようである。これは日本で調査するのは無理だが。
⑥花岡事件だけが極東軍事裁判でとりあげられ、木曽谷事件と結合しなかった。検事側は木曽谷事件も調査し、中国人証人も日本にとどまったのであるが、なぜか木曽谷事件および他の事業所で行われた戦争犯罪はとりあげられなかった。
⑦日本に残った花岡、木曽谷の数少ない中国人証人と日本人左翼の交流はなかった。
⑧強制連行された中国人、朝鮮人、台湾人の協働作業は、遺骨収集や闇市での出会いはあったが、それらは被害者当人たちの当然の交流であって、それを組織的・全国的に仲介する日本人グループはなかった。
⑨被害者と加害者日本人の対決はもっぱら被害者当人の努力によって行われ、日本の左翼が自己の責任で介在したケースはないはずである。
⑩直接の加害者、下手人の実存も切開されることなく、戦後過程で野ざらしである。
いま走り書いた諸点は、ことごとく日本問題である。ぜんぜん中国問題ではない。それはもっぱら日本側の責任である。
この中で秋田県花岡の人々がもっとも先進的であり、自分たちの生きかたとして『花岡ものがたり』をうんだことは特筆されるべきことである。その花岡においてさえ、遺骨収集活動は戦後五年を経た一九五〇年にはじまっており、中華人民共和国成立後にはじめられたということは、この問題にたいする日本人のおくれをしめしている。遅れたが、しかし三十年前にはじまったのであって、草の墓標がコンクリートで蓋をされた現在でも、一センチずつ、進めていくべきテーマだ。一センチ進むための一ミリが石飛仁のエリトゲである。全体は、そうだなあ、五万華里の長征くらいあって、そのなかの一ミリ。木刻のディティールにもどろう。
――木版画にしたのは……。
鈴木 すでにその頃、中国では大衆運動の出版物に版画が使われ、日本の版画家との交流が行われ、ヨーロッパの版画、エッチングなどにもつながる気運になっており、新居広治氏がその条件をぴったり備えていました。これを企画したK・М氏案では「押仁太」と称する三人組の共同作業との話もありましたが、三人の個性ある画家(新居氏、滝平二郎氏、牧大介氏)を一緒にするのはもったいないということで、新居氏一人にしぼってお願いしました。
新居さんは、このむずかしい問題にとりくむこととなって、花岡―県北の取材を終えて、いよいよ製作は県南の横手の私の家ですることになりました。
――新居さんの製作にかけられた情熱は大変なものと聞いていますが……
鈴木 そうです。私たち夫婦と私の母は、私の家で制作することになったことで大変感激して、家で一番明るい南側に製作室を提供し、寝室も別にして、食事も米のごはんを三度さしあげ、晩酌も欠かさないように母は気をつかっていました。先般、秋田のある新聞で(注――『大館日報』をさす)、私の家でコッペパンとドブロクで合宿したように紹介してありますが、決してそんなことはありません。この機会に新居さんのご家族のみなさんに弁明させてもらいます。その頃、滝平さんも時々尋ねてくれたように思います。版木も桜の最上のものを使いました。
来る日も来る日も朝から晩まで、花岡、花岡といって彫り続ける新居さんの姿が今でも目に浮びます。一日一枚できればよいほうで、蜂起後の虐殺、拷問の絵では、ついに寝込んでしまうありさまでした。新居さんはデッサン力のある人で、版画は力作です。スライドで大写しにした共楽館内での拷問の場をみましたが、表情のすさまじさには改めて圧倒されました。
これはいい話だと思う。版画づくりが、主として新居広治の努力によって行われたこと、調査し、取材し、製作するうちに事件が新居広治にのりうつってくるさまのなかに、当時の人々の活動が思い描かれて感銘する。『花岡ものがたり』の原本を僕は見たことはないのだが、同紙に写真版で挿入されているこの本の「あとがき」をぬきだしておこう。
花岡事件は、軍国主義日本の罪悪のかたまりのようなものである。これをてってい的に追求し、えぐりとることは古い日本の腐ったカスをなくして、日本と中国の本当の友好をきずくいしずえである。これをあいまいにのこしておくことは、軍国主義のばい菌をつちかっておくようなもので、ふたたびおそろしい戦争をひきおこすもととなる。
この絵ものがたりは、平和を愛し、日本を愛し、日中関係の永遠の友好をながう人々によって、一大国民運動をおこすためにつくられた。あらゆる困難をおかして、闇にほうむられようとする事件の真相について、調査に調査をかさね、これを、ほんとうにいきいきした芸術作品として表現するために、討論し、修正し、それこそ血の出るような努力がつみかさねられた。この作品は、在日家郷四万と日本の民衆のあいだにおこされた日中友好運動の力にささえられ、また、現地秋田の鉱山、山林労働者、農民及び民主的な団体とその運動に援助されつつ、友好運動者、画家、詩人、文学者、音楽家その他多くの人々の集団制作としてうまれたものである。これは日本の芸術運動の上に、あたらしい方向をきりひらいたものとして、芸術史の一頁をかざるものであろう。
この困難な、画期的な事業を遂行された関係者各位に感謝するとともに、読者の一人一人が日本のすみずみまで普及する一大国民運動に参加されることを期待してやまない。
一九五一・五・三〇 日本中国友好協会文化部
魯迅が提唱した連環図画がまさに『花岡ものがたり』に結実したことは疑えないものと思われる。その運動の現在的展開として、エリトゲ運動が存在することを俺は感じる。『大館新聞』『日中友好新聞』の両紙記事、『花岡ものがたり』あとがきの宣言的文章およびさきに引用した内山嘉吉論文をつきあわせたときに浮かびあがってくるものの一つは魯迅―嘉吉にはじまる中国版画運動が、二十年かけてふたたび嘉吉を介して、民衆的メディアとして『花岡ものがたり』に実現したということである。それからさらに二十年、石飛仁の劇団エリトゲに。あと三点補足しよう。
第一に新居広治の仕事、一九八〇年九月、水戸市の京成百貨店で新居広治遺作展がひらかれ、目録に、この美術家の画歴が紹介されている。一九一一(明44)年、東京生。一九二九年、青山学院中等部卒業後、岡田三郎助、前田寛治、牧野虎雄に師事して油絵を習得。一九三一年、プロレタリア美術家同盟に所属。一九三九年、尾崎三郎らと「日本美術家連盟」を創立したが、軍国主義的傾向に反対して脱会。一九四五年九月、海軍より復員後「人民美術会」を創立。入江弘、赤松俊子らと「民主主義美術界」を創設。一九四六〜七年、戦後初の高萩炭鉱労組の生産管理闘争の木版画シリーズを制作。一九五〇年、鈴木賢二、小口一郎、飯野農夫也、滝平二郎らの「版画運動協会」に参加、本格的に版画創作をはじめる。メキシコ、アメリカ、中国、ソ連、チェコ、デンマーク、東独などの日本版画展に出品。この年、『日立物語』『常東物語』の制作に参加。そして一九五一年、『花岡ものがたり』。一九五六年、中国で『花岡惨案』として再刊。一九五八年、連環図画集『水兵物語』完成。一九六四年、東独、キューバ、ルーマニアの日本版画展に出品、日中版画交流展に出品。一九七〇年、東独の世界版画ビエンナーレに招待出品し受賞。一九七二年、日本傑作絵本シリーズ『でらだぼう』(斎藤隆介作)版画イラスト制作。一九七四年九月十一日、東大附属病院で死去。六十三歳。
これでみられるとおり、彼は『花岡ものがたり』以前に、炭鉱夫の闘争を描いた木版画シリーズや、『常東物語』『日立物語』等の連環図画集を制作しているのである。
第二に魯迅の連環図画論。魯迅の基本的態度は「革命に役立つ木刻の創作とそれらを人民の中に普及させること」(内山嘉吉)である。蘇汶ら高踏派が連環図画に対して「確実に、連環図画はトルストイを生み出すことはできないし、フローベルを生み出すことはできない」と主張したことに対し、魯迅は批判をかえしていわく。
「左翼作家はいかにも高尚なものではない。連環図画、唱本は、しかし蘇汶先生が断定したほど見込みのないものでもない。左翼もトルストイ、フローベルは要る。ただ『将来に属する(彼らは現在は要らないからだ)ものの創造に努力する』トルストイやフローベルは要らぬ。この二人は、みな現在のために書いた人々だ」(内山嘉吉、前掲書より)
「魯迅が連環図画を弁護していたとき、茅盾も『連環図画小説』を発表、連環図画という形式を巧妙に応用すれば、必ずや大衆文化にとって有力な作品を生み出すであろう、そうなれば、絵、文章の両面にわたって『芸術品』の域に達することができると主張していることは注目してよい」(山嘉吉、前掲書)
第三に、五木寛之の小説『デラシネの旗』には、一九六八年パリの学生革命時、学生たちがポスター、ビラ、パンフにしきりに石版画を制作したことが描かれている。木版画、石版画、連環図画などは民衆的メディアとしてすぐれたものである。エリトゲに美術家の参加を希望する。
本年(一九八五)六月三十日、花岡事件四〇周年目に、秋田県大館市が「平和祈念事業」を主催することを決定した。「本年六月三〇日に花岡事件の四〇周年を迎えるにあたり、悲惨な事件であった事実は事実として認め、ここに殉難者の霊を慰めると共に、この事件を乗り越えて、広く世界の平和を希求し……(中略)西の広島、南の長崎の平和祈念運動とは原因の発生は異なるにしても、北の平和祈念都市大館市を全国的、世界的にアピールし、平和の輪を広げていきたい」(大館市平和祈念事業施行〈案〉概要)
大館市が平和都市宣言を行うのである。広島や長崎と「原因の発生は異なるにしても」、すなわち加害者としての都市だったということを明記して平和都市宣言を発することはこの市の見識である。
これにエリトゲは参加する。芝居の出前だ。劉智渠、李振平、宮耀光三氏の花岡行きも実現する。劉、李両氏が花岡に行くことははじめてであり、両氏と宮耀光氏が会うのも、極東軍事裁判以来、最初である。塚越正男氏も参加し、山東省で人狩作戦に参加した当事者兵士が、劉氏たちと会うのもこれが最初である。一センチ、前進することができるだろう。
『平民芸術論』 平岡正明 1993年11月15日 三一書房刊
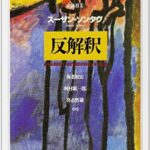 むかしむかしのことならば(高度な芸術が希少だったころならば)、芸術作品を解釈するということは、革命的な創造行為であったにちがいない。今日では、そうではない。いま断じて必要でない事、それはこれ以上さらに「芸術」を「思想」に吸収せしめること、あるいは(こちらのほうがもっと始末がわるい)「芸術」を「文化」に吸収せしめることである。
むかしむかしのことならば(高度な芸術が希少だったころならば)、芸術作品を解釈するということは、革命的な創造行為であったにちがいない。今日では、そうではない。いま断じて必要でない事、それはこれ以上さらに「芸術」を「思想」に吸収せしめること、あるいは(こちらのほうがもっと始末がわるい)「芸術」を「文化」に吸収せしめることである。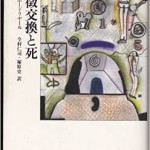
 昭和九年(一九三四年)に私は東京美術学校油画科に入学し、昭和十四年(一九三九年)に卒業した。われわれの世代は大正デモクラシーなるものを知らない。しかし昭和九年から十四年という時期は、戦前の日本経済が最も活況を呈した時であり、やがてくる戦争への不安をはらみながらも頽廃のムードを秘めて平和をむさぼっていた時から、二・二六事件や中華事変の勃発を挟んで、日本が急速度に軍国化へ傾斜しはじめるきわめて変化に富んだ時期にあたっている。事変勃発と同時に召集された親友Kが戦死し、卒業を真近に控えた頃、左翼的な思想をもつという理由で親しい友人の幾人かが警察へひかれていった。数年後に学生生活を送った人たちの多くが、軍国主義一色に染め上げられ、あるいは強制された時代に育ったとするならば、われわれは恵まれた学生時代を送ったということができるかもしれない。
昭和九年(一九三四年)に私は東京美術学校油画科に入学し、昭和十四年(一九三九年)に卒業した。われわれの世代は大正デモクラシーなるものを知らない。しかし昭和九年から十四年という時期は、戦前の日本経済が最も活況を呈した時であり、やがてくる戦争への不安をはらみながらも頽廃のムードを秘めて平和をむさぼっていた時から、二・二六事件や中華事変の勃発を挟んで、日本が急速度に軍国化へ傾斜しはじめるきわめて変化に富んだ時期にあたっている。事変勃発と同時に召集された親友Kが戦死し、卒業を真近に控えた頃、左翼的な思想をもつという理由で親しい友人の幾人かが警察へひかれていった。数年後に学生生活を送った人たちの多くが、軍国主義一色に染め上げられ、あるいは強制された時代に育ったとするならば、われわれは恵まれた学生時代を送ったということができるかもしれない。


